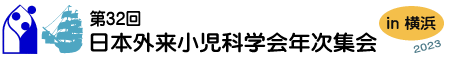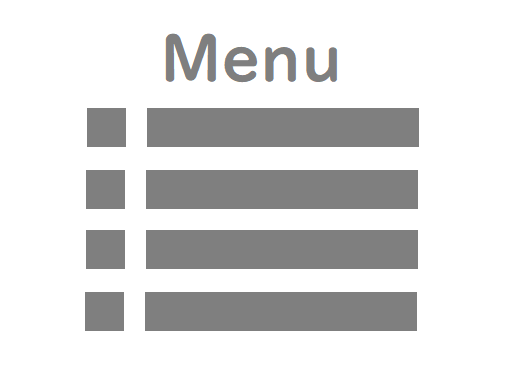企画のPR/【特別講演】小児ぜんそく治療の歴史(180度の大転換はどのようにしておこったのか)
ぜひ多くの参加者にこの講演を聞いていただき、次世代へのバトンのうちの「大切な1本」にしたいと思っています。(山本淳/星川小児クリニック)
どうしてもこの講演をお願いしたかった理由(わけ)
今回の年次集会、会頭講演ありません(笑)。でも、もし自分がたどってきた軌跡を振り替って、次世代の小児医療の担い手に伝えるとしたら、徳島大学の先輩でもある西川清先生と一緒に活動していた1990年代から2000年代にかけての、小児ぜんそく治療方針の大転換の歴史でしょうか。その講演は私よりも西川先生にぜひお願いしたいと、年次集会の準備をする最初から考えていました。
私自身は、たまたまその場(時代)にいただけですが、多くの先輩たちと一緒になって、何かおかしい、何をすればいいのか、いろいろと悩み続けながら目の前の患者さんと向き合う日々が続いていました。その頃の思いを、西川先生にもっと大所高所から凝縮してお話ししていただけたらと、この年次集会の「特別講演」とさせていただきました。
1990年代、年間6000人が喘息で死んでいました。
今と、何が違うのでしょうか。
薬が進歩したのでしょうか?
確かに、抗ロイコトリエン薬は登場していませんでした。しかし、吸入ステロイド薬はありました。
一番違っていたのは、私たちの治療への向き合い方ではなかったかと思います。
少しの症状は水を飲んで腹式呼吸をしてがまんをしましょうというわけで、喘息で入院した子に、お腹の上に砂袋(ウエイト)を載せて腹式呼吸の練習をしてもらっていました。
重症の患者さんは通学もままならないので、養護学校併設の療養所に長期入院してもらっていました。
そこでは鍛錬療法(運動、乾布摩擦、冷水浴)がひとつの治療の柱になっていたほか、全国の療養所では「親子(特に母子)分離」のために入院するのだという考え方も強かったと思います。「ペアレンテクトミー」という医学用語もありました。
「母原病」という言葉もありました。(検索すれば今でもでてきます)
喘息は親、とくに母親の育て方が原因で起こる(悪化する)という考え方です。
また、喘息は患者自身の心の問題という考え方も根強くあり、カウンセリングが必要ということが当たり前のように言われていました。
しかし、なぜ発作を起こしたのか、自分の心に聞いてみろと言われても・・・
実は私自身も、子ども時代は喘息児で、あと一歩のところで、療養所に送られるところでした。私の母もおそらくはその「母原病」という言葉を聞いて自問していたこともあるのかもしれません。そして多少なりとも影響されたかもしれません。
ところで、幸い私の喘息は寛解し、小学校の欠席も減り、いつしか、将来は工学部にすすみ、鉄道関係の仕事をしたいと思う高校生になっていました。
しかし、オイルショックが襲い、工学部を出ても就職先がないという状況の中で、友だちが医学部に進学すると言うので、じゃあ僕も医学部にでもいこうかなという曖昧な動機で医学部を受けたというのが、正直なところです。自分が喘息で苦しんだから、医師になって何かをしたいとかそういうことでは全くありませんでした(笑)。オイルショックがなかったら、新幹線を作ったり、JRに就職することができたかどうかはわかりませんが・・・
徳島大学の医学部3年生から4年生になる春休み、西川清先生(国立療養所香川小児病院)の診療を数日間の泊まり込みで見学させていただく機会を得ました。たくさんの入院児に囲まれ、信頼され、いつも話し相手になり、楽しそうに診療をされる先生の姿に憧れ、小児科医になりたいと思いました。まるでワイワイガヤガヤの寄宿舎のようでした。
その後、私は徳島を離れ、西川先生のご紹介で、神奈川県立こども医療センターアレルギー科で今でいう後期研修(1985~87)をさせていただきました。そこで、杉内政己先生に出会い、吸入ステロイド薬やDSCG+β2の定時吸入などを治療の中心に据えて、しっかりとコントロールすることで、気道過敏性(まだ気道炎症という言葉が無い時代)をじっくりと確実に改善させていくことを学びました。
西川先生も、そういった治療をいち早く取り入れ、「積極的ゼロレベル作戦」と名付け、入院児を片っ端から退院させていったというから驚きです。
しかし、そんな頃でも、「母原病」「鍛えて治す」「心の問題」「薬に頼らない」というような私にはどうしても受け入れられない言葉が耳に入ってきました。長期入院施設からの子どもたちの苦しむ声を聞こえてきました。
この状況は絶対におかしい・・・
私は、小児喘息は「楽をすればするほど良くなる実に都合の良い病気」だと言い、「ガイドライン通りに治療すると悪くなることもある」「QOLだけを指標にしていたらダメ」などと今だったらボコボコにされそうなことを各地で言って回るぐらいでしたが、西川先生は「積極的ゼロレベル作戦」という言葉を掲げて全国を走り回っていらっしゃいました。一緒に本も書かせていただきました。
喘息の子どもたちに我慢を強い、かえって悪くなるような治療から、今、若い先生たちが当たり前だと思っているような治療方針に変えるには、そしてそれを社会に受け入れてもらうには、西川先生たち先人の努力が必要だったのです。ベルリンの壁のように、大きな壁を壊す必要がありました。私見ですが、それは今まで多くの小児科医がしてきた治療方針を否定することにつながるからなのかなと思います。でも、その壁を壊さなくては、子どもたちの命を救うことができない(喘息は死ぬ病気でしたから)、前に進むしかありませんでした。
残念ながら杉内先生は若くしてお亡くなりになりましたが、西川先生や私の心の中に、しっかりとした治療方針として生きてくださっているのを今でも感じます。
もしかしたら、他の分野でも、「180度の大転換というような歴史」はあるのかもしれませんが、外来を担当する小児科医誰でもが診るぜんそくという病気を通して、「そのとき歴史が動いた」というような大転換への思いを、西川先生に語っていただき、次世代に伝えていきたいと思います。
おかしいと思ったときに、どうするか、「君たちはどう生きるか」、これはアレルギー以外の分野でも必要な考え方かもしれません。いや、医学に限ったことではなのかも。
「鍛錬療法」「母原病」そんな言葉聞いたこともない・・・そんな次世代の方にも、そして、久しぶりにその言葉を懐かしく、しかし思い出すのが辛いなと思われる年代の方々にも、ぜひ聴講していただけたらと思います。
私自身は、たまたまその場(時代)にいただけですが、多くの先輩たちと一緒になって、何かおかしい、何をすればいいのか、いろいろと悩み続けながら目の前の患者さんと向き合う日々が続いていました。その頃の思いを、西川先生にもっと大所高所から凝縮してお話ししていただけたらと、この年次集会の「特別講演」とさせていただきました。
1990年代、年間6000人が喘息で死んでいました。
今と、何が違うのでしょうか。
薬が進歩したのでしょうか?
確かに、抗ロイコトリエン薬は登場していませんでした。しかし、吸入ステロイド薬はありました。
一番違っていたのは、私たちの治療への向き合い方ではなかったかと思います。
少しの症状は水を飲んで腹式呼吸をしてがまんをしましょうというわけで、喘息で入院した子に、お腹の上に砂袋(ウエイト)を載せて腹式呼吸の練習をしてもらっていました。
重症の患者さんは通学もままならないので、養護学校併設の療養所に長期入院してもらっていました。
そこでは鍛錬療法(運動、乾布摩擦、冷水浴)がひとつの治療の柱になっていたほか、全国の療養所では「親子(特に母子)分離」のために入院するのだという考え方も強かったと思います。「ペアレンテクトミー」という医学用語もありました。
「母原病」という言葉もありました。(検索すれば今でもでてきます)
喘息は親、とくに母親の育て方が原因で起こる(悪化する)という考え方です。
また、喘息は患者自身の心の問題という考え方も根強くあり、カウンセリングが必要ということが当たり前のように言われていました。
しかし、なぜ発作を起こしたのか、自分の心に聞いてみろと言われても・・・
実は私自身も、子ども時代は喘息児で、あと一歩のところで、療養所に送られるところでした。私の母もおそらくはその「母原病」という言葉を聞いて自問していたこともあるのかもしれません。そして多少なりとも影響されたかもしれません。
ところで、幸い私の喘息は寛解し、小学校の欠席も減り、いつしか、将来は工学部にすすみ、鉄道関係の仕事をしたいと思う高校生になっていました。
しかし、オイルショックが襲い、工学部を出ても就職先がないという状況の中で、友だちが医学部に進学すると言うので、じゃあ僕も医学部にでもいこうかなという曖昧な動機で医学部を受けたというのが、正直なところです。自分が喘息で苦しんだから、医師になって何かをしたいとかそういうことでは全くありませんでした(笑)。オイルショックがなかったら、新幹線を作ったり、JRに就職することができたかどうかはわかりませんが・・・
徳島大学の医学部3年生から4年生になる春休み、西川清先生(国立療養所香川小児病院)の診療を数日間の泊まり込みで見学させていただく機会を得ました。たくさんの入院児に囲まれ、信頼され、いつも話し相手になり、楽しそうに診療をされる先生の姿に憧れ、小児科医になりたいと思いました。まるでワイワイガヤガヤの寄宿舎のようでした。
その後、私は徳島を離れ、西川先生のご紹介で、神奈川県立こども医療センターアレルギー科で今でいう後期研修(1985~87)をさせていただきました。そこで、杉内政己先生に出会い、吸入ステロイド薬やDSCG+β2の定時吸入などを治療の中心に据えて、しっかりとコントロールすることで、気道過敏性(まだ気道炎症という言葉が無い時代)をじっくりと確実に改善させていくことを学びました。
西川先生も、そういった治療をいち早く取り入れ、「積極的ゼロレベル作戦」と名付け、入院児を片っ端から退院させていったというから驚きです。
しかし、そんな頃でも、「母原病」「鍛えて治す」「心の問題」「薬に頼らない」というような私にはどうしても受け入れられない言葉が耳に入ってきました。長期入院施設からの子どもたちの苦しむ声を聞こえてきました。
この状況は絶対におかしい・・・
私は、小児喘息は「楽をすればするほど良くなる実に都合の良い病気」だと言い、「ガイドライン通りに治療すると悪くなることもある」「QOLだけを指標にしていたらダメ」などと今だったらボコボコにされそうなことを各地で言って回るぐらいでしたが、西川先生は「積極的ゼロレベル作戦」という言葉を掲げて全国を走り回っていらっしゃいました。一緒に本も書かせていただきました。
喘息の子どもたちに我慢を強い、かえって悪くなるような治療から、今、若い先生たちが当たり前だと思っているような治療方針に変えるには、そしてそれを社会に受け入れてもらうには、西川先生たち先人の努力が必要だったのです。ベルリンの壁のように、大きな壁を壊す必要がありました。私見ですが、それは今まで多くの小児科医がしてきた治療方針を否定することにつながるからなのかなと思います。でも、その壁を壊さなくては、子どもたちの命を救うことができない(喘息は死ぬ病気でしたから)、前に進むしかありませんでした。
残念ながら杉内先生は若くしてお亡くなりになりましたが、西川先生や私の心の中に、しっかりとした治療方針として生きてくださっているのを今でも感じます。
もしかしたら、他の分野でも、「180度の大転換というような歴史」はあるのかもしれませんが、外来を担当する小児科医誰でもが診るぜんそくという病気を通して、「そのとき歴史が動いた」というような大転換への思いを、西川先生に語っていただき、次世代に伝えていきたいと思います。
おかしいと思ったときに、どうするか、「君たちはどう生きるか」、これはアレルギー以外の分野でも必要な考え方かもしれません。いや、医学に限ったことではなのかも。
「鍛錬療法」「母原病」そんな言葉聞いたこともない・・・そんな次世代の方にも、そして、久しぶりにその言葉を懐かしく、しかし思い出すのが辛いなと思われる年代の方々にも、ぜひ聴講していただけたらと思います。
西川清先生から最初にいただいた抄録(ちょっと長すぎたので正式版は短くなりましたが)
小児喘息治療の歴史(180度の大転換はどのようにして起こったか)
現在気管支喘息の治療は、ICSを含む配合薬定期吸入や生物学的製剤の注射で、特に専門医でなくともコントロールが可能となりました。しかし30数年前まで、今では考えられないような病態解釈と治療法が採用されておりました。
単一疾患としては驚異の3-6%前後の有症率と、更に症状も呼吸困難・喘鳴とあまりに明白な疾患に対し、精神的疾患、母原病、β2吸入過使用による気道攣縮などが原因であり、ステロイド気管支拡張薬の手控え、鍛錬療法、両親離断療法、長期入院療法などが取り上げられ、学会では論客がこれらの効用を謳いあげ、ほとんどの医者がそれを信じ、それに従い、今考えれば全国津々浦々の医者が集団催眠にあるいはマインドコントロールを受けていたとしか考えられない状況にありました。
当時の患者たちの症状は非常に重症で、夜間救急外来やICUのメインの疾患であり、それでも薬を手控え、更に重症化し、喘息死も高頻度にみられておりました。
私も例にもれず、むしろ論客の一人として、様々な発表もし、ムンテラで患者を自身の無理やりな考えで説き伏せるのをむしろ得意がっていたものでした。
しかしそんな治療を続けていくうち、ますます発作洪水はひどくなり、発作に翻弄され疲弊し、自信を失い、何かにすがりたい、逃げ出したい、そんな気持ちになって参加したとある学会でβ2定期吸入の話を聞いたのです。DSCG+少量β2なら許されるのではと、入院時に定期予防吸入を始めたのが1987年4月の事でした。そして目の前には今まで経験したことのない治療効果が表れ、驚き、なぜ一様に効果が出たのか、では喘息の病態は何なのか、症例を重ねながら、その都度学会に報告しました。しかしそこには予想以上の逆風が吹き荒れ、以後5年に及ぶ学会での戦いが始まりました。
以後のお話は講演でお聞きいただきます。
現在気管支喘息の治療は、ICSを含む配合薬定期吸入や生物学的製剤の注射で、特に専門医でなくともコントロールが可能となりました。しかし30数年前まで、今では考えられないような病態解釈と治療法が採用されておりました。
単一疾患としては驚異の3-6%前後の有症率と、更に症状も呼吸困難・喘鳴とあまりに明白な疾患に対し、精神的疾患、母原病、β2吸入過使用による気道攣縮などが原因であり、ステロイド気管支拡張薬の手控え、鍛錬療法、両親離断療法、長期入院療法などが取り上げられ、学会では論客がこれらの効用を謳いあげ、ほとんどの医者がそれを信じ、それに従い、今考えれば全国津々浦々の医者が集団催眠にあるいはマインドコントロールを受けていたとしか考えられない状況にありました。
当時の患者たちの症状は非常に重症で、夜間救急外来やICUのメインの疾患であり、それでも薬を手控え、更に重症化し、喘息死も高頻度にみられておりました。
私も例にもれず、むしろ論客の一人として、様々な発表もし、ムンテラで患者を自身の無理やりな考えで説き伏せるのをむしろ得意がっていたものでした。
しかしそんな治療を続けていくうち、ますます発作洪水はひどくなり、発作に翻弄され疲弊し、自信を失い、何かにすがりたい、逃げ出したい、そんな気持ちになって参加したとある学会でβ2定期吸入の話を聞いたのです。DSCG+少量β2なら許されるのではと、入院時に定期予防吸入を始めたのが1987年4月の事でした。そして目の前には今まで経験したことのない治療効果が表れ、驚き、なぜ一様に効果が出たのか、では喘息の病態は何なのか、症例を重ねながら、その都度学会に報告しました。しかしそこには予想以上の逆風が吹き荒れ、以後5年に及ぶ学会での戦いが始まりました。
以後のお話は講演でお聞きいただきます。